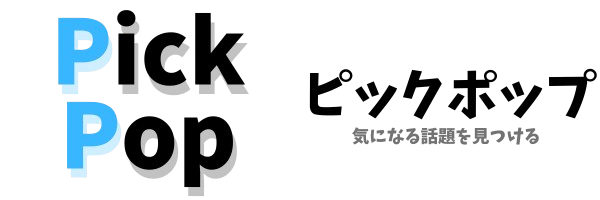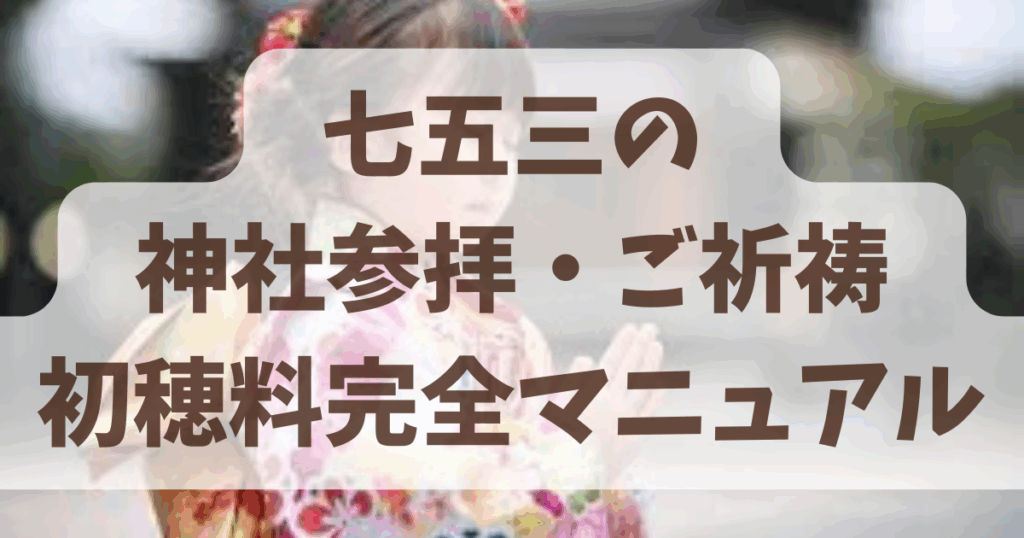
七五三は、お子さまの健やかな成長を祝い、これからの幸せを願う大切な節目です。
可愛い子供の大切な記念日。しっかり記念に残したいですよね。
でも実際には「神社参拝ってどう流れればいいの?」「ご祈祷は必須?」「初穂料っていくら?」と悩む声も多いんです。
この記事では、神社参拝からご祈祷、初穂料の準備までをわかりやすくまとめました。読んでいただければ、当日スムーズに動けて、家族全員が笑顔で七五三を楽しめるはずです。
七五三の神社参拝の基本

七五三の中心となるのは神社参拝。お子さまの成長を神様に感謝し、今後の健康を願います。
参拝のポイントは、「混雑を避けた日程選び」と「家族みんなでお参りする準備」。特に人気の神社は、土日祝日や大安などは大行列になることも。可能であれば平日を選ぶと、落ち着いて参拝や撮影ができますよ。
また、参拝時には「撮影OKかどうか」を事前に確認するのも忘れずに。神社によっては境内撮影が制限されている場所もあるので、事前チェックが大切です。家族写真は一生の宝物になるので、参拝と撮影をセットで考えておきましょう。
さらに、神社選びも大切なポイントです。格式の高い有名神社は雰囲気も厳かで記念になりますが、その分混雑しやすい傾向があります。一方で、自宅近くの氏神様(地域の守り神)に参拝するのもおすすめです。身近な神社は子どもにとっても親しみやすく、これからも折に触れて参拝できる「思い出の場所」にできます。家族のスタイルに合わせて「華やかにお祝いしたい」「落ち着いて記念にしたい」など希望を整理し、最適な神社を選んでみましょう。
七五三の神社選びについて

七五三は基本的に どの神社でも参拝・ご祈祷できます。
特に「ここでなければならない」という決まりはありません。
選び方の主なパターン
- 氏神様(近所の神社)
地域の守り神に感謝を伝えるという意味で最も自然な選択肢。
→ これからもお祭りや初詣で訪れる機会が多く「成長を見守ってもらえる」という安心感があります。 - 有名・格式ある神社
例:明治神宮、日枝神社、川崎大師など
→ 七五三の雰囲気を華やかに楽しみたい家族に人気。記念撮影スポットも豊富ですが、その分混雑もしやすいです。 - ゆかりのある神社
両親が結婚式を挙げた神社、祖父母が通っている神社など。
→ 家族の思い出をつなぐ場として特別感が増します。
ご祈祷は受けるべき?その意味と流れ
神社参拝だけでも十分ですが、せっかくなら「ご祈祷」を受けることで、より特別な体験になります。
ご祈祷とは、神主さんに祝詞をあげてもらい、子どもの健康や成長を祈っていただく儀式です。所要時間は15〜30分程度。お守りや千歳飴を授与してくれる神社もあります。
当日は、待ち時間が発生することもあるので、お菓子や飲み物を持参しておくと安心です。小さな子はじっと座っているのが大変なので、親が寄り添って「あと少しで終わるよ」と声をかけてあげるのがポイントです。
初穂料とは?金額の目安と包み方
「初穂料(はつほりょう)」は、ご祈祷をお願いする際に神社へ納める謝礼のこと。金額は神社によって異なりますが、一般的には5,000円〜10,000円が相場です。
熨斗袋に「初穂料」または「玉串料」と書き、子どもの名前をフルネームで記載するのが基本マナー。紅白蝶結びの水引がついた袋を選ぶと安心です。
ここで大切なのは「気持ちを込めて納めること」。金額の多い少ないよりも、「子どもの成長を感謝する気持ち」を大切にしましょう。なお、金額や書き方は神社によって指定がある場合もあるため、必ず事前に公式サイトや社務所で確認しておくことをおすすめします。
参拝・ご祈祷の持ち物チェックリスト
当日忘れ物をすると、バタバタしてしまって写真どころではなくなります。以下のリストを前日までに準備しておくのをお勧めします。
- 初穂料(熨斗袋入り)
- 千歳飴用の袋(持ち帰りに便利)
- 草履や足袋(履き替え用にスニーカーもあると安心)
- タオルやウェットティッシュ
- お菓子・飲み物(子どもの待ち時間対策)
- カメラ・スマホ・予備バッテリー
この準備があるだけで、当日のスムーズさが段違いになりますよ!
まとめ
七五三は、お子さまだけでなく家族全員にとって大切な思い出になります。
神社参拝で感謝を伝え、ご祈祷で特別な時間を過ごし、初穂料で気持ちを形にする。
ひとつひとつの行動に意味があり、その積み重ねが「最高の記念日」になります。
ぜひこの記事を参考に、準備万端で七五三を迎えてくださいね。
最後にもうひとつ。参拝やご祈祷、初穂料の細かいルールは神社ごとに異なる場合があります。必ず公式サイトや社務所に確認してから当日を迎えてくださいね。
「よし!これで安心して七五三に行ける!」と感じていただけたら嬉しいです。親子揃って最高の記念日になりますように。