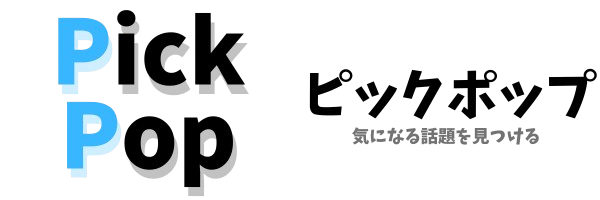毎年9月1日は「防災の日」。
大きな地震や台風が多い日本では、自分や家族、大切な人たちを守るための備えを見直す大切な日でもあります。
特に小さなお子さんがいる家庭では、非常食や防災グッズだけでなく、子どもと一緒に「もしもの時どうするか」を話し合っておくことが安心につながります。
でも「どうして9月1日なの?」「学校や保育園ではどんなことをしているの?」「家庭では何を備えればいいの?」と、気になることもたくさんありますよね。
この記事では、防災の日の由来や意味から、学校や保育園での取り組み、家庭で役立つ防災グッズまでまとめました。
忙しい毎日でも、少しずつでも備えられるヒントやきっかけを見つけていただけたら嬉しいです。
防災の日とは?その意味と由来
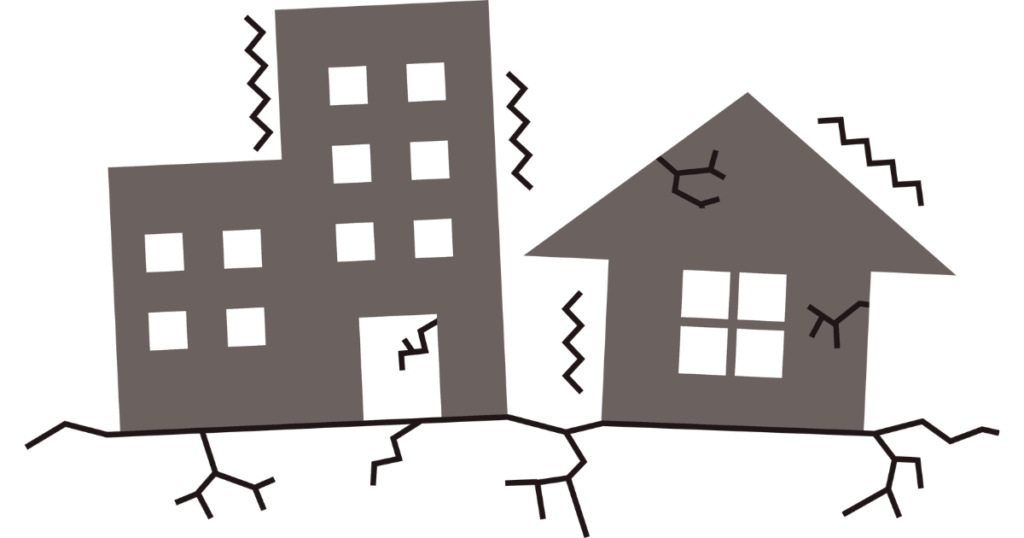
制定の背景と目的
「防災の日」は、自然災害の多い日本で、防災意識を高めることを目的に制定された記念日です。地震・台風・津波などの被害を教訓に、国民一人ひとりが「もしもの時」に備えるきっかけとするために設けられました。
関東大震災と防災の日の関係
1923年9月1日に発生した関東大震災は、死者・行方不明者10万人以上という甚大な被害をもたらしました。この出来事を忘れず、防災意識を受け継ぐために「防災の日」が定められています。
「9月1日」になった理由
台風が多く「二百十日」と呼ばれる時期でもある9月1日は、自然災害に備える象徴的な日です。関東大震災の発生日でもあり、気候的にも警戒すべき日とされました。
なぜ防災の日ができたのか
過去の災害を教訓とし、国や自治体だけでなく家庭や学校・職場でも防災意識を育てる必要があると考えられたためです。「自助・共助・公助」を意識するきっかけとして定着しました。
防災の日はいつ?祝日なの?
防災の日は9月1日
防災の日は毎年9月1日です。2025年も変わらずこの日となります。
祝日ではない理由
「防災の日」は国民の祝日ではなく、記念日です。そのため会社や学校が必ず休みになるわけではありません。
振替休日・学校休みになるのか?
祝日ではないため、振替休日も存在しません。学校によっては防災訓練が実施されるケースがあります。
防災の日は毎月あるの?(毎月1日との違い)
「毎月1日が防災の日」と思われることもありますが、正式には9月1日のみです。ただし地域によっては「毎月の訓練日」を定めている場合もあります。
防災の日の歴史と雑学
制定日と誰が決めたのか
防災の日は1960年(昭和35年)、内閣の閣議了解によって制定されました。
関連する記念日(防災週間・防災月間など)
9月1日を含む1週間(8月30日~9月5日)は「防災週間」とされています。さらに9月全体を「防災月間」とし、全国で啓発活動やイベントが行われます。
100年を超える歴史と豆知識
2023年は関東大震災から100年という節目であり、防災の日の重要性が改めて見直されました。
世界・海外の防災の日
世界的にも「防災の日」に相当する日が存在します。たとえば国連は「国際防災の日」(10月13日)を制定しています。
防災の日のイベント・訓練
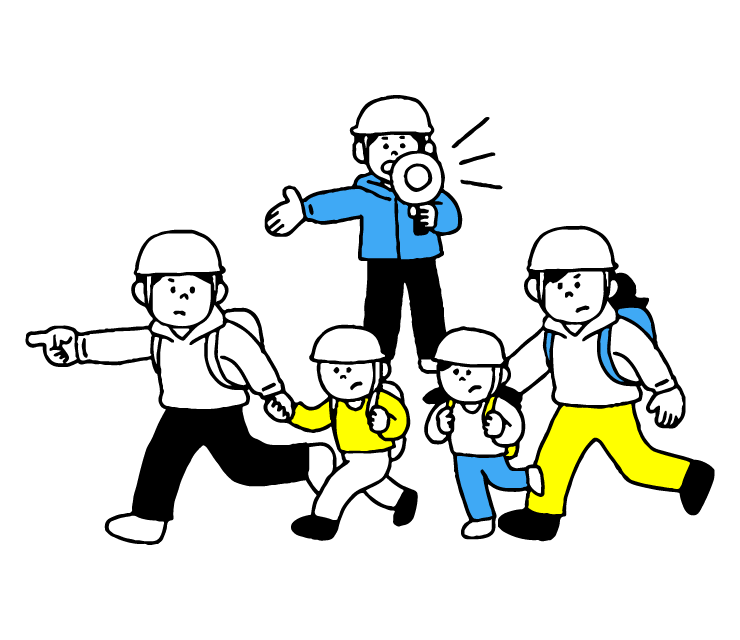
全国各地で行われるイベント(東京・大阪・横浜・札幌など)
各自治体で、防災フェス・展示会・シミュレーション体験などが開催されます。親子で参加できるものも多く、体験を通じて学べる場となっています。
防災訓練の種類(避難訓練・引き取り訓練・総合防災訓練)
- 避難訓練:地震や火災を想定した避難行動
- 引き取り訓練:保護者が子どもを迎えに行く訓練
- 総合防災訓練:消防・自衛隊・警察と連携した本格的な訓練
中止になった場合の対応(例:2024年)
感染症や天候の影響で中止になるケースもあります。その場合は家庭で自主的にチェックリストを確認することがおすすめです。
企業・自治体による取り組み
企業のBCP(事業継続計画)訓練や、自治体の避難所運営訓練など、多方面で実践的な防災活動が進められています。
学校・保育園での防災の日

子ども向けの活動(紙芝居・クイズ・レクリエーション)
子どもたちには難しい防災知識も、紙芝居やクイズ形式なら楽しく学べます。
保育園のおたより・園だより・保健だより
防災の日に合わせて、園から「防災だより」が配布されることがあります。家庭でも備えを確認するきっかけになります。
学校給食や特別献立(すいとんなど)
防災食をテーマにした給食が提供されることがあります。例として「すいとん」は関東大震災を象徴する食事として知られています。
朝礼やスピーチのネタ
学校や職場で「防災の日の話題」を取り上げることが増えます。短いスピーチでも「備えの大切さ」を伝える機会になります。
防災教育で大切にしたいポイント
「なぜ必要か」を丁寧に伝えることが重要です。特に子どもには体験を通じて学ぶ機会を設けると理解が深まります。防災に対する意識を持つことは自分を守ることに繋がるので、子供が理解するまで伝え続けることが大切ですね。
備えと防災グッズ

家庭で用意したい防災グッズ
最低限必要なのは「水・食料・ライト・ラジオ・モバイルバッテリー・救急セット」。防災リュックにまとめておくと安心です。
これらをまとめた「防災リュック」なら一度に揃えられ、いざという時にすぐ持ち出せます。
楽天では【防災リュックセット】【一家用非常持ち出し袋】などが豊富に販売されています。
備蓄食・非常食・ローリングストック
カンパンやアルファ米だけでなく、レトルトや缶詰も活用できます。普段の食事に取り入れて「使いながら備える」ローリングストックが推奨されています。
カンパンやアルファ米のほか、温めなくても食べられるレトルト食品や缶詰も人気です。
「ローリングストック(普段食べながら買い足す方法)」を取り入れると無理なく続けられます。
楽天では【アルファ米セット】【長期保存水】【非常食3日分セット】などが売れ筋。
ペットのための備え
フード・トイレシーツ・キャリーケースなど、人間と同様に備えが必要になります。いざという時に大切なペットを守る準備をしておくといいですね。
【ペット用防災セット】【犬・猫用フード保存パック】は楽天で簡単に購入できます。
防災フェアやセール情報
9月前後は防災の日に合わせて、ホームセンターやECサイトでセールが行われます。
「まとめ買い」「セット商品」がお得になるタイミングを狙うのもおすすめなのでチェックしておきましょう!
ポータブル電源や最新グッズ
停電対策としてポータブル電源やソーラーパネルが注目されています。家庭用に小型モデルを一台備えておくと安心です。
スマホや家電を充電できるため、子育て世帯や在宅ワーク家庭でも注目されています。
楽天では【小型ポータブル電源】【ソーラーパネル付き充電器】が人気。
防災の日にできること
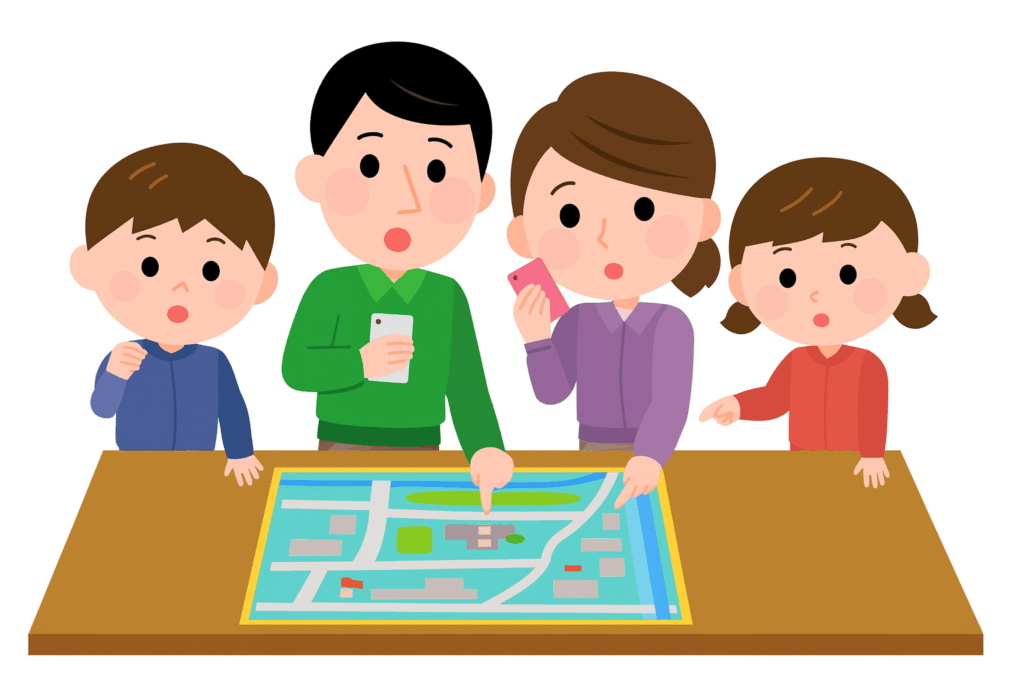
家族での安否確認方法
「災害用伝言ダイヤル(171)」やLINE・災害時安否確認サービスを家族で共有しておきましょう。
スマホアラート・エリアメールの確認
緊急速報の受信設定を見直すことも、防災の日の大切な習慣です。
家庭での防災チェックリスト
非常食・水・充電器・避難経路などを年に一度見直しましょう。
朝礼やスピーチで伝えたいメッセージ
「災害は必ず起こるもの。備えることが命を守る第一歩」というシンプルな言葉が響きます。
「防災の日」をきっかけにした話し合い
家族で避難場所や連絡方法を確認する良い機会です。子どもにもわかりやすく伝えると効果的です。実際に避難場所まで足を運んでおくと、いざという時に行動に移しやすいのではないかと思います。
まとめ
防災の日は「過去の災害を忘れない」ための日であり、「防災意識を高める記念日」となります。
家庭・学校・地域での取り組みが未来の安心につながります。まずはできることから一歩ずつ行動するのが大切。
「防災の日」をきっかけに、ぜひ家庭の防災グッズや備えを見直してみましょう。
楽天では、防災リュックから非常食・ポータブル電源まで一度に揃えることができるのでチェックしてみてください。